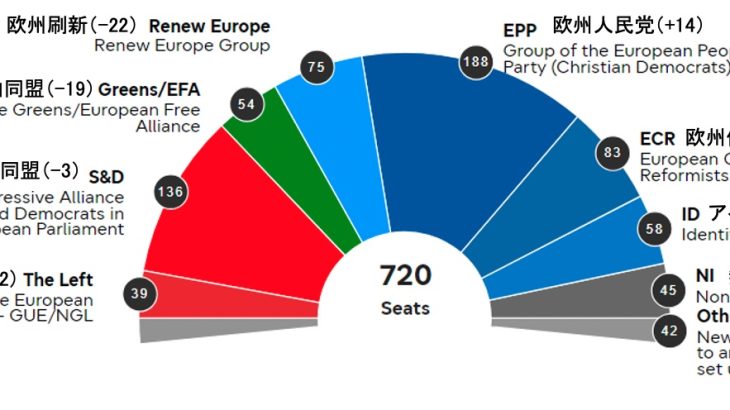白川真澄
2023年度の政府予算案が2月28日、大きな抵抗もなく衆院を通過し、年度内成立が確実となった。しかし、この政府予算は、軍事費だけを制約なしに増やす異様なものである。「国のかたち」を根底から変えるような戦後最悪の予算であり、声を大にして批判する必要がある。また今後、予算の執行に必要な法案(例えば「防衛力強化資金」の創設のための「防衛力財源確保特措法」)の成立を阻むために力を尽くさなければならない。
予算案の規模は114兆3812億円と、22年度より6.3%、6.8兆円も増え、あっさりと110兆円を突破した。過去12年間の当初予算の増え方は平均1.5%、1.5兆円ずつだったから、「平時」としては、いかに異常な増え方であるかが分かる。
その元凶はいうまでもなく、防衛費の突出した増額である(表1)。
《表1 2023年度予算案/歳出と歳入の主要項目》
■歳出
総額 114兆3812億円(+6兆7848億円、6.3%増)
社会保障関係費 36兆8889億円(+6154億円、1.7%増)
防衛費 6兆7880億円(+1兆4193億円、26.4%増)
防衛力強化資金繰り入れ 3兆3806億円(+3兆3806億円、新設)
公共事業費 6 兆0600億円(+26億円、0%増)
文教・科学振興費 5兆4158億円(+257億円、0.5%増)
予備費 4兆円(-1兆円、▲20.0%)
地方交付税 16兆3992億円(+5166億円、3.3%増)
国債費 25兆2503億円(+9111億円、3.7%増)
■歳入
総額 114兆3812億円(+6兆7848億円、6.3%増)
税収 69兆4400億円(+4兆2050億円、6.4%増)
国債 35兆6230億円(-1兆3030億円、▲3.5%)
税外収入 9兆3182億円(+3兆8828億円、71.4%増)
( )内は22年度からの増減と伸び率
防衛費増額の異常な突出
防衛費は6.8兆円で、22年度から1.4兆円も増え、伸び率は26.4%である。安倍政権の下で防衛費が増えつづけてきたとはいえ、それでも年平均615億円、1.1%の増え方であった。つまり、2013年度から昨年度までの10年間で6145億円増えただけである。それと比べると、今回の増え方はケタが違う。また、防衛費は、当初予算だけではなく補正予算でさらに増やす悪慣行(「15カ月予算」)が定着し、22年度も当初予算の5兆3687億円が5兆8469億円に膨らんだ。その水準からでさえ1兆円もの増額である。
さらに、「防衛力強化資金」なるものを新設して、これに3兆3806億円を繰り入れる。したがって、防衛費の総額は10兆1606億円(前年度から+4兆7919億円)にまで増える。歳出全体の8.9%を占めることになり(昨年度は5.0%)、公共事業費(6.0兆円)や文教・科学振興費(5.4兆円)を大きく引き離して社会保障関係費に次ぐ巨額の支出項目となる。
このように、防衛費は、これまでの対GDP比1%、年5.4兆円の水準から対GDP比2%、年10兆円の水準へと一気に跳躍した。防衛省が、今年度の防衛予算を「防衛力抜本的強化『元年』予算」と銘打って胸を張ったのも当然であろう。
その背景にあるのが、ウクライナ戦争の勃発を投影した「台湾有事」を想定した安保関連3文書の改定(22年12月16日の閣議決定)である。これは、米国が「唯一の競争相手」である中国にもはや単独では対抗できず、日本の軍事力の抜本的強化と共同の運用を求めたものである。そこでは、「現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であり、……最大の戦略的な挑戦であ」る(「国家安全保障戦略」)と記された。
そして、軍事力の抜本的強化の「鍵となるのは、スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力」の保有である、とされた。そのために、23~27年度の防衛費を従来の1.6倍の43兆円にまで増やすことを決めたのである。防衛費10兆円は、そのスタート=「元年」なのだ。
防衛省は「防衛力の抜本的強化」のために重視する7つの能力を掲げているが、とくに重点を置くのが「スタンド・オフ防衛能力」と「統合防空ミサイル防衛能力」の強化である(5年間の契約ベースで、前者には5兆円、後者には3兆円)。この2つが、今年度の防衛費増大の眼目となっている。
スタンド・オフ防衛能力の強化(「相手の脅威圏外からできる限り遠方において阻止する能力を高め、抑止力を強化」)には、中国沿岸部に届く長射程の「12式地対艦ミサイル能力向上型」の開発・量産(23年度は開発に338億円、量産に939臆円)、島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発(2003億円)、極超音速ミサイルの研究(585億円)、さらに巡航ミサイル「トマホーク」の米国からの購入(2113億円)が含まれている。その数が400発であることを、岸田首相はようやく白状した。
また、統合防空ミサイル防衛能力の強化(相手国の「弾道ミサイル・巡行ミサイル・極超音速滑空兵器に対する迎撃能力を強化」)には、イージスシステム搭載艦の整備(2208億円)、PAC-3ⅯSEミサイルの取得(421億円)が含まれている。
「反撃能力」は誰のために行使される?
「反撃能力」の保有は具体的には、中国沿岸部を先制攻撃できる長射程(1000キロ以上)のミサイルやトマホークを南西諸島に配備することにほかならない。岸田政権は、こうした能力を備えれば、相手国(中国)は報復されることを恐れて日本への攻撃を思いとどまるにちがいないと言う。すなわち、「反撃能力」の保有は、日本への攻撃を諦めさせる「抑止力」として働く、というわけである。
しかし、日本が新たに先制攻撃能力を保有すれば、中国は対抗してさらに強力なミサイルを開発・配備しようとするだろう。反撃能力の保有は、相手国を挑発し、いっそうの軍備増強を加速させる引き金になるだけである。また、中国のミサイル基地すべてに壊滅的な打撃を与えようとすれば、自衛隊が予定している程度の「反撃能力」ではとうてい不可能である。とてつもなく強大な軍事力をもつことが必要になるが、それは米軍と一体になった軍事力としてのみ可能なのである。
「自分の国を自分で守る」ために反撃能力の保有が必要だ、といった言説が流布され、多くの人がそのように思い込んでいる。しかし、これほど大きな錯誤はない。この反撃能力は、日本が自らの判断で単独で行使するものではないのだ。それは「日米が協力して対処していく」(「国家安全保障戦略」)と明記されている。反撃能力の運用、すなわち敵基地を攻撃する長射程ミサイルの発射は、米軍だけが知りうる情報によって米軍とともに、というよりも米軍の判断と指揮の下でだけ行われるのである。

このことを示すのが、新たに明記された「統合防空ミサイル防衛」の構築(「国家防衛戦略」)である。米軍は、陸海空や宇宙・サイバーなどあらゆる手段を用いて相手国の攻撃に対応する「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」の構想を2017年から推進してきた(図参照)。IAMDは、ミサイルの迎撃にとどまらず、相手国のミサイル基地を叩くことで「武力攻撃そのものを抑止する」(「国家安全保障戦略」)とされる。そのためには敵基地攻撃能力の保有が必要不可欠だが、日本は今回これをクリアすることによって、IAMDを構築することが可能になったのである。日本が瓜2つのIAMDをもつことは、相手国へのミサイル攻撃において米国に「融合」することを意味する。
そもそも中国が日本を攻撃することがあるとすれば、それは、「台湾有事」(台湾への中国の武力侵攻)の勃発に対して米軍が介入し、日本が米軍と一体になって行動する場合である。すなわち、在日米軍基地が出撃拠点とされ、自衛隊が米軍を支援し、南西諸島の自衛隊のミサイルが発射準備に入る。そうなれば、これらが間違いなく中国の標的にされる。裏返せば、在日米軍基地からの出撃を「事前協議」(日米安保条約の)で認めず、米軍への支援行動を行わず、南西諸島のミサイル基地を撤去する。同時に、台湾への武力侵攻をやめるように中国との対話を積極的に行なう。こうすれば、中国が日本を攻撃する必要性も理由もまったくなくなる。
このように、反撃能力の保有とは、日本が米軍の始める戦争の最前線を担うことを意味する。つまり、米軍の攻撃能力を補い、より強めることに役立つだけなのだ。そして、南西諸島や沖縄の住民を再び「捨て石」として戦火にさらすリスクを高める。こうした反撃能力の保有のために、軍事費を年10兆円にまで膨らませることは歴史的な愚行であり、「平和国家」の建前を完全に脱ぎ捨てる暴挙でしかない。
増やしていない子育て支援の予算
防衛費の異常な増額とは対照的に、他の項目の増え方は低く抑えられている。
最も重要な社会保障関係費は36.9兆円で、前年度から6154億円増、1.7%の伸びである。防衛費に比べると、伸び率は16分の1にすぎない。高齢化の進行に伴う自然増だけでも7800億円になるはずだが、薬価引き下げや後期高齢者の自己負担額の引き上げなどによって6000億円程度の増額に抑えられた。内訳は、年金13.0兆円、医療12.2兆円、介護3.7兆円、福祉(少子化対策、生活保護など)7.8兆円となっている。
社会保障のなかでも最大の焦点になっているのは、子育て支援の強化である。岸田首相は、昨年の子どもの出生数が80万人を切ったことに焦燥感をもち、「異次元の少子化対策」、「子ども予算の倍増」をぶち上げている。ところが、予算案のなかの子ども・子育て支援は、4兆8104億円と、前年度から1223億円増えただけである。育児休業給付などを加えた「少子化対策予算」は、6.1兆円になる。
しかし、この予算では、出産一時金の引き上げ(42万円 → 50万円)、妊娠・出産した人への10万円の給付が目立つ程度である。児童手当が大幅に増えるわけでも、保育士の数が増えて保育サービスが安心して受けられるようになるわけでもない。
子育て支援強化の中身も、金額も、財源も何ひとつ示さず、ただ「異次元」や「倍増」の言葉だけが踊る。追及されると、岸田は6月の「骨太方針」(経済財政諮問会議)で決めると逃げまくる。子ども・子育て支援への公的支出は、日本が対GDP比で1.8%である。フランスの3.6%、スウェーデンの3.4%、OECD平均の2.3%(2017年)をずっと下回っている(岸田は、現在は対GDP比2%だと言っている)。だから、「倍増」と言うのなら、子育て支援には対GDP3.6~4.0%分、約20~24兆円を支出しなければならない。つまり10兆円以上増やす必要があるはずだ。しかし、岸田は「倍増」するベースが何であるかさえ明言しない。防衛費倍増の悪印象を和らげるために、子育て支援「倍増」の看板を掲げただけなのだろう。
子育て支援の強化には何が必要か
私たちは、国家が経済成長や国力増強のために出生数を増やそうとする「少子化対策」を批判する。しかし、子どもを持ちたい人が「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」という理由(理由の60%)で希望を断念しているとすれば、この社会的・経済的な障壁を取り除くのは、政府の役割である。
その点から見ると、現在の子育て支援の政策には大きな限界や穴がある。
(1)児童手当の支給。
現在は、中学生(15歳)までの支給に限られ、所得制限がある/3歳未満が月1.5万円、3歳~中学生が月1万円。所得660万円(収入額875.6万円)以下の世帯に限定。所得660~896万円(収入額1124万円)の世帯は特例給付一律月5000円、所得896万円以上は給付なし。
(2)保育サービスの提供。
現在は、保育所などの3~5歳児はすべて無償、0~2歳児は住民税非課税世帯が無償、幼稚園の3~5歳児は月3.7万円まで無償(消費税率10%への引き上げの見返りに2019年10月から導入)。また、保育士の配置基準は、保育士1人が3歳児20人を、4歳児以上30人を世話するという無茶なものになっている(イギリスやドイツでは、1人が5歳児13人をケアする)。そのため、保育士の目や注意が行き届かず、事故や虐待が多発している。賃金が極めて低いこともあって、人手不足が深刻である。保育士の数は65万人だが、資格を持っていても働いていない潜在保育士は102万人もいる(日経新聞23年2月6日)。
(3)子どもの医療費や給食費の無償化。
子どもの医療費を中学生まで助成したり無償にする自治体が増えてきた(約60%、2018年)。また、給食費の無償化も広がっている。
(4)大学生・専門学校生への支援。
大学や専門学校の学費は、圧倒的に自己負担になっている。50万円以上仕送りしている家庭は73.9%(2020年度、日本政策金融金庫の調査)に上る。給付型奨学金(91万円)と授業料減免(70万円)を利用できるのには所得制限があり、大内佑和によれば利用者は全体(340万人)の1割弱にとどまっている。
(5)子育て世帯に対する住宅手当。
日本では、「住まいの権利」が人権として保障されてこなかった。そのため、OECD加盟国では30ヶ国にある公的な住宅手当がまったく支給されていない(生活保護世帯への住宅扶助だけ)。政府の持ち家取得促進政策によって、住居の確保は自己責任とされてきた。家賃の支払いに苦労する貧困・低所得層のみならず、子育て世帯にとっても住み替えなど住宅にかかる負担が重くのしかかっている。
したがって、子育て支援の強化には、次のような施策が必要になる。
(1)現在の児童手当を、所得制限を撤廃し、18歳までの子ども全員に一律に給付する/18歳以下の子どもは1918万人(21年10月1日時点)だから、1人当たり月2万円給付すると4.6兆円が必要になる(現行の1.2兆円よりも3.4兆円増)。
(2)保育士を抜本的に増やす/保育士の配置基準を、先進的な自治体の水準に引き上げ、保育士1人が世話する子どもの数を3歳児15人、4~5歳児20人にする。そのために保育士を増やす必要があり、平均給与を少なくとも労働者全体の平均並みに引き上げる。保育士の数を90万人に増やし給与を月6万円引き上げるには、新たに1.4兆円が必要になる。
(3)それ以外に、子どもの医療費を高校生まで無償化する(現在は明石市、東京都など)。すべての大学生・専門学校生に対して給付型奨学金+授業料減免の措置をとる(5.5兆円)。低所得層への住宅手当支給の制度を導入する(山内康一は、住民税非課税世帯に月2万円を支給するために2.7兆円の予算を提案)。
大軍拡か、いのちと暮らしか
このように、子どもを安心して育てることができるためには、巨額の財政支出が求められる。(1)の児童手当の拡充と(2)の保育士の増員だけでも、新たに4.8兆円が必要になる。あるいは、フランスやスウェーデン並みの子育て支援を行なうには10兆円の追加支出が必要になる。しかし、これこそ最優先で急いで実行すべき支出である。
それでは、この財源をどのように確保すればよいか。
第1に、人を殺す防衛費の倍増をやめ、さらに装備品購入費や研究開発費(併せて1.6兆円)をばっさり削減する。今年度の予算案では、これによって5兆円以上を確保できる。
第2に、富裕層と大企業への課税強化を実行する。具体的には、金融所得課税を累進課税とし、所得1億円以上の富裕層の税負担を重くする。また、大企業の内部留保(21年度末)が前年度より17.5兆円も増えている現状を踏まえ、法人課税を強化する。そうすれば、10兆円の財源が捻出できる。
なお、金融所得への課税は一律20%であったが、今年度から強化措置が導入された。だが、それは見せかけにすぎない。すなわち、所得が年30億円を超える人に限って、合計所得金額から3.3億円を差し引いた上で22.5%の税率をかける。この額が通常の税額より大きければ、その差額を徴収する、という措置である。年200~300人だけが対象となる。だが、所得が1億円を超える人は2万7395人(21年)いるから、そのわずか1%にだけ課税を強化する。ひどい茶番劇である。
私たちに問われているのは、何を優先するのかという政治選択である。大軍拡か、いのちと暮らしか。「国」の安全(実は米軍)を守る軍事費の倍増か、いのち育て守る子育て支援支出の大増額か。答えは明かである。
[補足]
防衛費の倍増を賄う財源の調達をめぐって、増税ではなく国債を増発すればよいという主張が自民党内安倍派から出されている(萩生田政調会長)。軍事費増大のための増税はむろのこと、戦時国債の苦い経験から国債発行も許されない。しかし、子育て支援の強化のためには増税ではなく、国債を発行すればよいという主張(「子ども国債」論)も出ている。
今年度の国債発行額は35.6兆円と、前年度から1.3兆円減っている。昨年度の税収が過去最大の68.4兆円に増えたことが要因だが、防衛費が急増したために僅かな減少にとどまった。しかし、新規国債以外に借換債157.5兆円など国債発行総額は205.7兆円にもなる。その結果、普通国債残高は23年度末には25兆円増えて1068兆円、対GDP比187%に達する。
こうした巨額の政府債務を積み上げることは、ただちに財政破綻を招かないとしても、大きなリスクをもたらす。その1つが、長期金利の上昇に伴う利払いの増大である。日銀の金融緩和路線の弊害が目に見えて大きくなり、その転換は避けられなくなっている。となれば、国債増発のハードルを下げてきた長期金利は、必ず上昇する。今年度の国債費(利払い+償還費)は25.2兆円と、昨年度から9111億円増えている。財務省の最新の試算では、金利上昇に伴い26年度の国債費は29.8兆円に増えるが、金利が想定より1%上振れすれば33.4兆円と、今年度より8.1兆円も膨らむ。
アベノミクスの異次元金融緩和によるゼロ金利の下で、いくらでも国債を増発することができると思いこんできた観念(それを正当化したMMT)は、もはや通用しないのだ。
(2023年3月5日記)