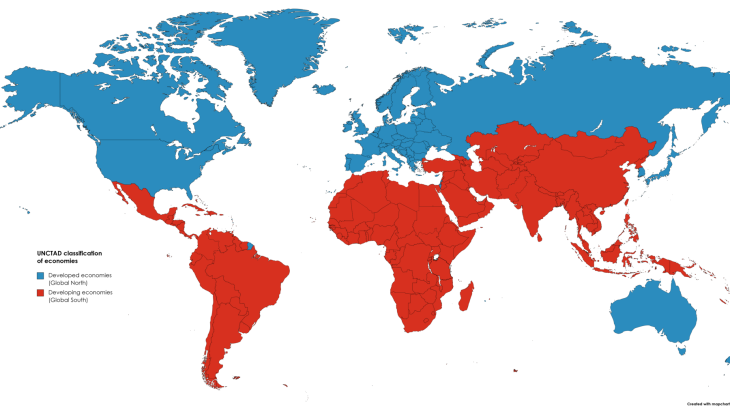WAVE出版、2024年、1600円+税 長澤淑夫
本書は、「人新世」を切り口として、幅広く、複眼的に人類史を論じた好著である。「地球環境の破壊といった外側からの異変とともに、さらに奥深い人間世界の変貌、一種の進化史的な変化として進行している」人新世は、複合的な変化(科学、技術、文化、経済)が驚異的なスピードで進んでいる時代であると古沢氏は把握している。この「人新世」の登場以来、多くの議論が巻き起こったが、それらを紹介し、議論の飛び交う範囲と意味をうまくまとめた本書は人類の来し方行く末を考える上で有益と考え、紹介の筆を取った。以下、内容を簡単に紹介し、論じていく。
- プロローグー地球史とヒトの出現をたどる (1章から3章)
一般に、地質年代は地球内部の力や自然力による地表の変化を示す歴史区分であるが、ヒトが出現して以降、自然を改変する活動により深刻な影響が地球に生じた。この状況に対し、従来の地質区分ではない把握が必要と考える人々が、「人新世」なる地質年代を提唱したという(2000年代初頭)。そしてこの考え方は人文社会科学から文化芸術の分野にまで広く浸透していく一方、地質年代の専門家は2009年から「人新世」の定義をめぐる活動を続けているという。著者は近年の人類活動が地球環境に与える影響は甚大だとし、気候変動をその例として紹介した後、地球誕生から人類の出現までの気の遠くなる歴史を手際よくまとめ、論じている。
さらに人類の出現後、ホモ・サピエンスは、脳を大きくし、道具の利用、思考・コミュニケーション能力を発達させ、幾多の大きな気候変動に対応しつつ、他の動物に勝利した。その後さらに文化を発展させ続けたことを論じ、この要因としてリチャード・ドーキンスが提唱する「文化の継承と発展を担う文化的自己複製子ミーム」を援用し、遺伝子だけでは説明できない農耕・牧畜以降の発展を説明している。そして一万年後の産業革命までは安定した気候の中で人間は発展してきたが、20世紀後半以降には危機的な気候変動を経験するようになったという。
近年さかんになっている野生の動植物の家畜化の研究を示した後に、人間の自己家畜化という興味深い仮説を紹介している。これは「ヒトの進化の過程では、共感能力や協調行動が過酷な環境を生き抜くために重要なことから、集団生活においての従順さや協調性を発揮する幼形成熟の特徴が作用し」、「新たな環境への適応力が格段に高められ」たという説である。近年の研究から、人間はもっとも寛容でもっとも残虐というブライアン・ヘア説や「友好性とともに攻撃性が生じてくる矛盾」を考察したリチャード・ランガムを紹介し、戦争やジェノサイド、ナショナリズムを考える上ではこの議論は興味深いとし、「仲間との一体感(共感能力)は、対抗する敵対者への強い反感や憎悪を生むという両面性を持つのです。」と著者はコメントしている。ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルによるガザでの虐殺の一面を、この議論は説明しているだろう。
第二部 展開編 人間拡張のゆくえ (4章から6章)
能力の外部化とは道具の利用によって、身体的な能力を補い代替するだけでなく、身体の外に能力を拡張していく可能性が開かれたことの重要性を著者は指摘し、特に脳の能力では、言語によって、概念やシンボルや物語、さらに数字、記号、音楽、宗教、貨幣、市場・・それによって国家といった高度な社会・文化的発展を実現していった、と論じている。ここでユヴァル・ノア・ハラリの「シンボリックな虚構を作り出して共有する力こそが、ヒトを勝者にした」(『サピエンス全史』)という議論を、肯定的に紹介している。遺伝子の働きだけでは人間とならず、ケアと教育の重要性を著者が論じた箇所は、「ヒトは文化によってつくられ、社会的に形成されていく生物」で「その文化や道具は、外の環境に応じて変化し、適応していく可能性(フレキシビリティ)と創造性(クリエイティビティ)の上に築かれています」という指摘に呼応している。これは重要な指摘だと私は同感した。
「5章 ヒトからトランスヒューマン」では、近未来論を多数紹介しつつ論評を加え、未来を語る一方で直視すべき現実として軍事衝突や戦争をおこす人間のアンビバレントへの自覚を、古沢氏は求め、新家畜化という興味深い概念を紹介している。この概念に対して、「私たちは自らが創りだした巨大システムによって養われる存在」で、それを維持しつつもそれへの関与は希薄化していると著者は問題点を指摘している。多数の未来論を論じた理由は、複眼知(多様な視点)から世界を重層的、立体的にとらえるためだったとし、この章をまとめている。
そして「6章 『人新世』の落とし穴」ではふたたびハラリを登場させ、彼が、ポスト・ヒューマン的な人間を「ホモ・デウス」という造語で示したことを紹介している。AIとロボット技術、ゲノム編集技術と相まって新たな人種の出現がここでは想定されている。具体的にはイーロン・マスクのような活力に満ちたスーパーリッチが「ホモ・デウス」そのものに見えると著者は論じている。その裏では監視資本主義のもとで過酷な労働を強いられる事態が欧州では生じていることを紹介している。また未来予測は現状肯定派と否定派に分かれ、正反対な未来像を描きがちとだとし、客観的なデータをもとに検討していく必要を指摘し、世界経済フォーラムで毎年発表される「グローバルリスク報告書」を紹介している。この報告書は中長期的なリスクの動向を経年的に確認できる利点をもっているとし、数例を挙げている。報告書で「地経学上の対立」が上位に浮上していることについては「経済戦争の常態化で大国間の争いが激しさを増し、緊張状態が続いている影響でしょう」と古沢氏は判断している。人口動態については、歴史的・人類史的変化を分析しているエマニュエル・トッドの『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』(文藝春秋、2022年)を紹介し、人口推計としては原俊彦『サピエンス減少 縮減する未来の課題を探る』(岩波新書、2023年)や国連の推計などを元に21世紀後半にピークを迎え、22世紀以降は減少していく、とまとめている。
人類が環境危機や人口減少を、資本の適正なコントロールとテクノロジーの民主化によってうまく回避したとしても、生命科学やAI・情報工学には新たなリスクがありそうと、著者は予測し、遠未来にサピエンスが迎える三つの展開を提示している。「ひとつは、仮想世界が現実世界を凌駕し、仮想と現実を快適に交流・交換できる世界」(新・家畜化社会)」、「もうひとつは、仮想世界の拡大が現実世界に影響し、『スター・ウォーズ』のような宇宙世界へと進出していく展開」。「もうひとつは、前者と後者が合わさったり、住み分けたりするような展開」。「私たちヒトが本当のところどんな未来を望んでいるのか、人間の幸福とは何かにまで、話はいきつく」と著者はまとめ、第二部を閉じた。
「第Ⅲ部 エピローグ 『人新世』の未来」では、危機打開の糸口として、国連加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のために2030アジェンダ」を取りあげ、そこに見られる民族や国民という意識から、地球市民的な意識への変化に著者は期待を寄せている。長い人類の歴史が危機を乗り越えたように、「人新世」を生きる私たちの道の持続を期待し、「世界が ぜんたい幸福にならないうちは 個人の幸福はありえない」から始まる一節を宮沢賢治『農民芸術概論綱要』から引用し本書を締めくくった。
著者は、未来はこうなる、と結論しているわけではない。危機を意識しつつ、人は未来に向かってどのみち生きていく。その生きるにあたり様々な分岐点では、あれやこれやと迷いながらも、「世界や歴史を多様な角度から立体的にとらえる複眼的知」と「物事の関係性や矛盾を見極める洞察知」、「世界や他者と自分との関係性に心をよせる共感知」をもって、人間は進んでほしいとの著者の願いは本書から十分に伝わってくる。他方、デヴィッド・グレーバーは遺著『万物の黎明』(光文社、2023年)で、発展段階的でないでホモ・サピエンス登場以来の興味深い歴史的実践を提示した。この議論に入る余地は古沢氏の著書にあるのだろうか、との感想をもちつつ筆を置く。