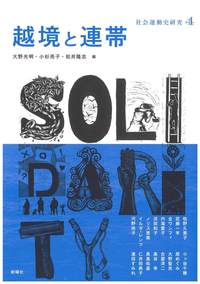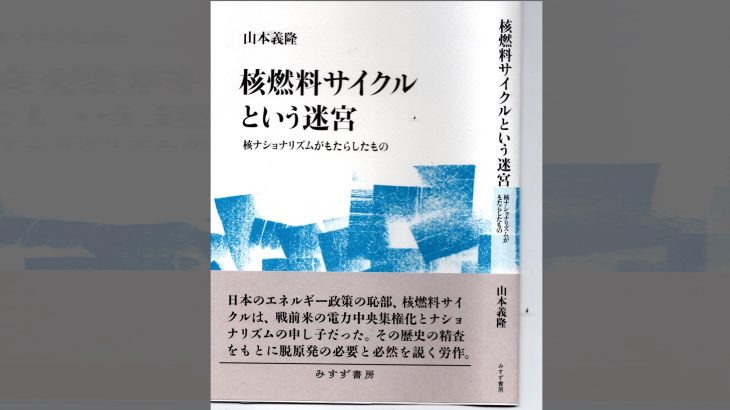大野光明・小杉亮子・松井隆志編(新曜社)
2300円+税・2022年刊行
本書が発刊されたことを知ったのは知人のSNSの投稿だった。SOLIDARITY、版画で描かれた力強い文字の連なりが目に飛び込んでくる表紙が目に留まった。しかしながら、「積読」状態の本に囲まれ、そのままになってしまっていた(ゴメンナサイ…)ところ、とある会合で編者の松井隆志さんから書評をお願いしたい、とお声がけいただく。曰く「越境と連帯」に関わる「若手」で、「過去の運動史に多少なりとも興味を持」っている筆者に、ということだった。多様な論考やインタビュー記事はどれも示唆深いものだったが、字数の関係もあり、私が特に関心を持った論考に焦点を当てて話を進めたい。
その一つが、牧野久美子さんによる論考「反アパルトヘイトの旅の軌跡——「遠くの他者」との連帯のために」だ。大学卒業後、1年弱の会社勤めの後にNGOの世界に飛び込み、インドネシアや東ティモール、フィリピンなどの東南アジア島嶼部地域に関わって十余年が経った。自分自身の「越境」はもちろん、異なる地域・立場の人びとの「越境」体験を手伝ってきた経験と重なって、大変興味深く拝読した。アフリカに関しては門外漢だが、境界を越える人の移動=「旅」というものがもたらす他者との出会い、それによって具体的に「顔が見える関係」が構築された結果として、運動が結成され、拡大・持続していったという反アパルトヘイト運動の事例は、80年代に呼びかけられたネグロス・キャンペーンにも重なる。
マルコス独裁政権下のフィリピン・ネグロス島の人びとを襲った深刻な飢餓。その救援のためのキャンペーンの事務局として設立されたのが「日本ネグロス・キャンペーン委員会(JCNC)」、私が活動するNPO法人APLAの前身となる市民団体である。JCNCは、発足直後からのネグロス現地の調査活動と並行して、フィリピン教育演劇協会(PETA)の俳優を招聘しての日本縦断コンサートツアーを企画。1986年4月の東京を皮切りに、約1か月の間に計24回のコンサートを実施したという記録が残っている。その後、全国各地でJCNCネットワークが誕生する原動力となったのがこのコンサートだった。その基盤には、1970年代から90年代にかけて、マルコス独裁政権を支える日本政府の援助、日系企業の公害輸出など、日本の加害者性と正面から向き合いながらフィリピン民衆との連帯運動を展開してきたフィリピン問題連絡会議(JCPC)の存在があったことは明らかだ。しかし、キリスト教会や労働組合が主体であったり、女性が中心になったりと、メンバーの顔ぶれ豊かなネットワークが日本各地で構築されたのには、「現地の人びととの顔の見える関係の確立と、支援状況の実態を見ることを目的とした交流ツアーの実施。また、現地から人を招き直接実態を知らせてもらうこと」というJCNCが掲げた基本方針によるものだろう。そのことを牧野さんの論考によって再確認することができた。
反アパルトヘイト運動の中心的な担い手となる人びとの「旅」はもちろんのこと、日本がアフリカを搾取するという一方的な関係を変えるための草の根の交流の機会の創出、反アパルトヘイト市民運動そのものの実践として展開されたという「オルタナティブ・ツアー」にも注目したい。1986年にスタートし、アパルトヘイト廃止の後も2017年まで続いていたというが、このツアーを通じてアフリカと出会った人びとの体験もまた、いつかは運動史の一部として刻まれることになるのだろうか。アフリカ、アジアと地域は異なれど、「旅」を通じてもたらされた「顔のみえる関係」の先に広がっている世界を共に見てみたい。
順番が前後してしまうが、私が本書に関心と共感を持って向き合えた理由に、巻頭の編者3名による「越境と連帯の運動史——日本の「戦後」をとらえかえす」があるということを伝えておきたい。いわゆる国際協力分野で活動するNGO関係者、特に同世代や若い仲間たちには、まずはこの巻頭文だけでもぜひ読んでもらいたいと思う。
COVID19のパンデミックで大きく事情が変わったとはいえ、ひと昔前に比べれば国境を越えるハードルが色々な意味で低くなった時代に成長した我々の世代(ミレニアル世代と呼ばれたりする)、さらには物心ついた時からインターネットによる情報収集が当たり前となっているデジタルネイティブのZ世代には、「支配のシステムは境界線をつくり出しながら、暴力と抑圧を維持している。これらと闘い、システム自体を変えていくために、人びとは境界線を揺さぶり、越えていくことが必要になる」という提起にピンとくる人はどれほどいるのだろうか。ふと、そんなことを考えた。
かくいう私自身が「境界線」について、初めてじっくりと考察したのは、20歳の頃だったと思う。大学の講義室でおもむろにナマコやフカヒレ、ツバメの巣を取り出しながら、「海は境界ではなく道なんだ」と話してくれたのは、故村井吉敬さん。東南アジア海域でとれる高級中華料理食材というモノを通じて、国境という国家と国家の境界線を、軽々と越えてきた/越えているヒトたちの存在を知らせてくれた。目から鱗が落ちる、まさにそういう講義だった。それが入り口となって、自分が絡め取られている境界線についても思いを巡らせるようになった。生まれ育った日本という国の中に引かれた多数の見えない境界線、それを意識し、越えていくことをフィールドワークという形で後押ししてくれたのも村井ゼミだった。2004〜2005年当時、沖縄県名護市辺野古でのボーリング調査の強行を阻止するために海上やぐらでの座り込みに参加していたゼミの先輩がいた。彼女が伝えてくれる現場の現状、何よりも彼女の放つ熱によって、自分には見えていなかった境界線が克明に浮かび上がり、それまで他人事として捉えていた沖縄の基地問題との向き合い方が変化した(とはいえ、私自身が主体的に関わるようになったのは、それから10年近くも後のことだ)。
大野光明さんの論考「アメリカ人留学生のベトナム反戦運動——太平洋を横断する運動空間のなかの沖縄」では、1970年代の米国の反戦グループ、パシフィック・カウンセリング・サービス(PCS)の沖縄における運動と留学生の関わりについてが、当事者へのインタビューや一次資料から明らかにされている。3名の留学生のライフヒストリーに、日本留学前に東アジアでの生活や滞在=「越境」の経験があるという共通点があることは興味深い。境界線の向こう側に関心を持った若者たちが、太平洋を越えて、日本の反戦運動と出会い、合流し、沖縄でPCSの立ち上げに関わり、米軍基地のフェンスが隔てた人びとのあいだの連帯をつくろうとした。その若者たちの軌跡を追体験するような感覚で本論考を読み進めたが、1971年の全軍労のストライキの現場でのPCSの活動に特に自分の中の何かが共鳴した。写真の中で「彼ら[全軍労労働者]のストライキはあなた/わたしを徴兵するシステムに対するものだ」という手書きの横断幕を持って立つ3人の留学生。彼女たちのもとに駆け寄りたい、そんな思いに駆られたと言ったら皆さんに笑われるだろうか。
50年前に、米国からの留学生によって米軍基地の前で掲げられたこの横断幕のメッセージは、沖縄県民の民意を徹底的に無視し続け、莫大な税金を投入して、辺野古の新基地建設が強行されている現在、基地の中の米兵以上に、意識的か無意識的にかにかかわらず、「境界線」のこちら側でシステムの維持に加担してしまっている人びとに届けなくてはいけないものではないか。「彼ら[市民の]の新基地建設阻止行動はあなた/わたしを戦争に巻き込むシステムに対するものだ」という形に置き換えて。
最後になるが、半世紀も前に、太平洋をはさんだそれぞれの反戦運動が沖縄という地で交差し、共鳴し、大きなうねりを創り出したという事実が、本書をはじめとした運動史の共有によって、広く知られることを願ってやまない。「越境と連帯」の歴史的事実は、キャンプシュワブのゲート前で、辺野古・大浦湾の海上で、高江の座り込みテントで、平和を求めるあらゆる現場で、いまこの時も行動しつづけている一人ひとりにとって、過去から現在、未来につながる大きな励ましになるはずだから。
野川未央(のがわ・みお) 特定非営利活動法人APLA事務局長