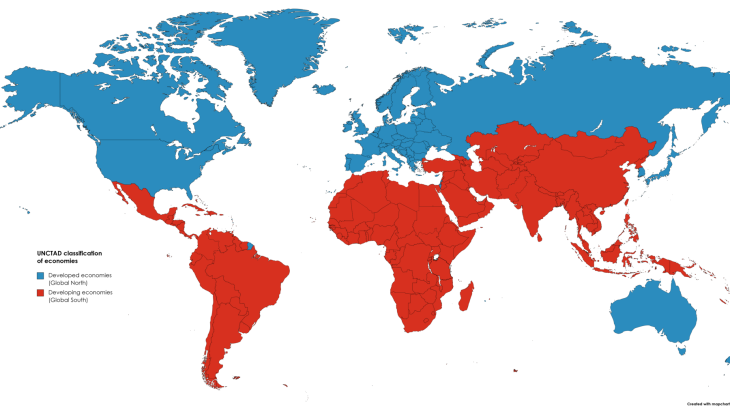白川真澄
岸田政権の支持率の低落がどうにも止まらない。マスコミの11月の世論調査では軒並み3割を切って(毎日:21%~NHK:29%)、危険水域に入った。この政権の先が長くないことを告げる。さらに、パーティ券裏金作り問題が追い打ちをかけている。
象徴的なのは、起死回生を狙って打ち出した1人4万円の所得減税と7万円の現金給付を柱にした大型の経済対策(11月2日閣議決定)が、多くの人びとの不評と不信を買ったことである。
17兆円を超えるこの経済対策の中身に立ち入ってみると、支離滅裂としか言いようがない。まったく矛盾する施策が平気で並べられていたり、ごまかしやすり替えが随所に見られる。人びとから見透かされても当然である。その支離滅裂ぶりは、次の3つのことに表われている。
(1)減税するが、増税する/所得税・住民税を減税すると同時に、防衛費のために増税する。
(2)インフレが続いているのに、デフレから脱却することをめざす/物価高対策(インフレで苦しくなっている生活への支援)のはずなのに、「デフレからの完全脱却」が目的とされる。
(3)税収が増えているはずなのに、大量の国債を発行する。
所得減税分が防衛増税で取り返されることは、見抜かれている
岸田政権の経済対策の看板メニューは、所得税・住民税の定額減税である。1人あたり所得税3万円、住民税1万円を24年1年に限って減税する。扶養家族も対象とし、夫婦と子ども2人の場合は4万円×4人=16万円の減税となる。その対象は8600万人、3兆円台半ばの金額となる。「過去2年間で所得税・住民税の税収が3.5兆円増加」したので、「納税者である国民に分かりやすく『税』の形で直接還元する」(「デフレ完全脱却のための総合経済対策」11月2日)というわけである。
しかし、所得税も住民税も納めていない低所得層は、減税によっては何の利益も得られない。そこで、年収255万円以下の低所得世帯(約1500万世帯、2500万人)には1世帯あたり7万円(すでに決定済みの3万円と合わせて10万円)の現金給付を行う。
また、両者の狭間にある住民税は課税されるが所得税は非課税の世帯(~年収270万円程度、約500万人)には、住民税非課税世帯と同じ10万円を給付する。さらに、4万円の減税を受けきれない層(~年収310万円程度、約400万人)には、25年度分の住民税からも減税を検討する。
この減税と現金給付は、家計にどれくらいの効果をもたらすのだろうか。総務省「家計調査」によれば、非課税世帯が含まれる年収下位10%の世帯(世帯年収183万円以下)を除く世帯の平均消費支出は、月25.8万円(2022年)であった。世帯人員は平均2.34人なので、1人あたり年4万円の所得減税は、世帯の平均可処分所得を月0.8万円増やすことになる。これは、平均消費支出の3%分に相当する。23年10月の消費者物価指数(総合)は、3.3%の上昇だったから、3%分の負担軽減は物価高による家計への悪影響の大部分を緩和することになる。また、住民税非課税世帯への給付10万円は、年収下位10%の世帯の年間消費額の7%に相当し、物価高による負担増加分を大幅に上回る※1。
こう見ると、所得減税と現金給付は(所得減税は即効性がなく、実感できるのが24年6月になってからだが)、家計を圧迫している物価高の影響を取り除くだけの金額である。にもかかわらず、6割から7割(NHK:59%~朝日:68%)の人がこれを「評価しない」としている。その理由として挙げられているのは、「選挙対策に見えるから」がトップである(NHK:38%、読売:44%)。しかし、たとえ選挙対策であっても家計が潤えば支持されてもよいはずだが、これほど悪評を買うのは、なぜか。
2024年に1回切りの減税がされても、25年以降に防衛費増大の財源として所得税を含む増税(1兆円)が恒久的に行われることを、誰もが知っているからだ。岸田は、「所得税減税と防衛力強化への税制措置は矛盾しない」(記者会見、11月2日)と言い張る。だが、この説明に「納得できない」人は7割(NHK:67%、朝日:74%)にも上る。直後の防衛増税が所得減税を相殺してしまい、減税分がすぐに取り返されることは、容易に見抜かれる。
岸田は、減税と増税がなぜ両立できるのかという理由を説明できない。推測すると、所得税減税が賃上げと相まって可処分所得を押し上げることによって、消費支出が増えて経済が成長する、そこで可処分所得がさらに増えるから、増税しても負担が増えない(国民負担率が下がる)、とでも考えているのかもしれない。
このことと関連して、岸田の説明の力点は、所得減税・現金給付の目的が物価高対策や国民への「還元」よりも「デフレからの脱却」と経済成長の復活にあるということにシフトしていく。
※注1:神田慶司「所得減税は効果も必要性も疑問」、『週刊ダイヤモンド』23年11月25日)
インフレ(物価高)が続いているのに、「デフレ脱却」をめざすというすり替え
日本経済は、デフレ(物価の継続的な低下)ではなく、インフレ(物価の継続的な上昇)が続いている局面にある。消費者物価(総合)は、直近(23年10月)が前年同月比3.3%、15カ月連続(22年8月~)で3%超えが続いている。生鮮食品を除く総合(コア指数)でも、直近が2.9%、19カ月連続(22年4月~)で2%超えが続いている。とくに生鮮食品をのぞく食料は7.6%の上昇で、家計を苦境に追い込んでいる。
にもかかわらず、岸田政権は経済対策の目的をインフレ(物価高)対策よりも「デフレ脱却」としている。「総合経済対策」の目的も、「デフレ完全脱却のため」と銘打たれている。所得税減税は、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置」とされる。そして、岸田は、「デフレ脱却」の必要性を乱発している。「まず、経済活性化。……。今まさにデフレ脱却できるかどうかの瀬戸際だ」。「経済対策の規模は17兆円前半程度。最優先はデフレから脱却し経済を成長経路に載せることにある」(記者会見、11月2日)。
これだけインフレが長く続き人びとの生活を苦しめているにもかかわらず、政府は現状を‟デフレではないが、デフレを脱却していない”と言い続けてきた。「現時点では、『物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みはない』という状況には至っていない」※2。
政府はこれまで、デフレ脱却に向けての判断の根拠として4つの指標を挙げてきた。①消費者物価指数、②GDPデフレーター(=名目GDP÷実質GDP、総合的な物価動向)、③単位労働コスト(=名目雇用者報酬÷実質GDP、賃金動向)、④需給ギャップ(総需要と供給力の差)。
4つの指標を見てみると、①の消費者物価指数は、コアで19カ月連続して2%超えが続いている。②のGDPデフレーターは、22年10~12月期からプラスに転じ、23年4~6月が3.5%、7~9月期が5.1%になっている。③の単位労働コストは、23年1~3月期に一時的にマイナスになったが、大幅な賃上げの影響を受けて4~6月期に0.9%(前年同期比)の上昇に転じ、7~9月期も0.5%のプラスであった。④の需給ギャップは、19年10~12月期以来マイナスが続いてきたが、23年4~6月期に13四半期ぶりに0.2%のプラスに転じた。ただし、7~9月期は実質GDPが▲2.1%(前期比年率)になったため、需給ギャップも再び▲0.5%のマイナスになった。とはいえ、金額では3兆円程度のマイナスであり、需給ギャップはほぼ解消されつつある、と言える(例えば、21年の4~6月期の需給ギャップは▲4.0%、約25兆円にもなっていた)。
政府の重視する4指標から見れば、「デフレ脱却」を宣言してもよいはずだが、なぜか頑なに拒んでいる。再びデフレに逆戻りする恐れがまだあるからだというわけだ。その根拠として持ち出されるのが、現在のインフレが資源の高騰と円安に起因する輸入インフレであり、賃金上昇が物価を押し上げるようなインフレになっていないという見方である。
そして、岸田は従来の4指標に代えて、「賃上げが物価高に追いつく」あるいは「物価高を上回る」ということをデフレ脱却の新しい指標として主張しはじめた。しかし、これは、試合の途中でゴールや判定基準を変えるようなことである。
しかも、この新しい指標は、実に奇妙なものだ。米国では、この2年間の急激なインフレ期に賃金上昇率が物価上昇率に追いつかず、実質賃金は低下し続けてきた(ようやく23年1~3月期に賃金上昇率が6.1%と物価高5.8%を上回った※3)。新しい指標によれば、米国もデフレ脱却をしていなかったことになる。
そもそも、物価上昇が賃金上昇よりも先行する、したがって物価高に追いつこうとする賃上げの動きが強まるのが、インフレの特徴なのである。その意味でも、現在の局面がインフレ期であることは明らかだ。なお、この岸田の言い分を受け入れて無批判に繰り返している言説も少なくない。「賃金上昇が高い物価上昇率に追いついていない」からデフレを脱却できておらず、来春の賃上げが「日本経済が『緩やかなインフレ』に転じるためのカギを握る」(日経新聞23年12月2日)。すでにインフレが続いている現実を認めようとしない見本である。
デフレなのかインフレなのかは、物価(消費者物価上昇率、GDPデフレーター、企業物価指数など)が継続的に下落しているか上昇しているかによって決まる。インフレは、異なる多様な要因や経路によって引き起こされる現象である。需要の急速な増大、賃金コストの上昇、輸入品の高騰、為替の変動など。その要因や経路によってインフレの性質や特徴に違いが生じるし、対応策も異なってくる。しかし、どのような要因や経路によって引きこされたとしても、物価が継続的に2%を超えて上昇していればインフレ、すくなくとも緩やかなインフレなのである。
※注2:内閣府『経済財政白書』2023年版、P67
3:Bloomberg、23年4月19日
「『デフレ』の亡霊」に頼るムダな財政支出拡大の正当化
政府は、インフレ、すなわち「物価高から国民生活を守る」と言いながら、頑なに「デフレを脱却していない」と言い募る。その理由は明らかだ。赤字国債の増発による財政支出の拡大、それを支える金融緩和の継続という従来の政策をズルズル続けるフリーハンドを握るための正当性を保持したいからである。「物価高を抑えるためのガソリン補助金も含め13兆円という巨額の補正予算を正当化するには『デフレ』という亡霊に頼らざるをえない」※4、という批判は的を射ている。
インフレの時期には、デフレ期とは明確に異なる政策が求められる。物価高に苦しむ多くの人びとへの生活支援金(物価手当)の給付、公共交通機関の運賃の引き下げのための補助金、再エネや食料自給のための補助金などに多くの財政支出が行われねばならない。したがって、インフレ期だからといって必ずしも緊縮財政が採られる必要はない。しかし、需要不足を補うことを意図する財政拡大は正当性を失う。不要・不急な財政支出は削減され、赤字国債の発行も抑制されねばならない。
ところが、岸田「経済対策」を担保する23年度補正予算は、13兆1992億円(定額減税の分を合わせると17兆円台前半)と巨額なものになっている。補正予算の規模は、コロナ危機の20年度(73.0兆円)以前は平均3.3兆円(2013~19年度)であったから、平時としては異常な大きさだ。実に多くの不要で有害な支出項目が数多く盛り込まれたからである。
例を挙げれば、ガソリン価格高騰抑制のための補助金:1532億円※5、大阪・関西万博の事業費:750億円、自衛隊の運用態勢の早期確保(スタンド・オフ・ミサイルの早期確保など)、米軍再編の着実な実施(馬毛島の空母艦載機の移駐など):6617億円、マイナカード取得環境の整備:899億円、防衛費強化基金への繰り入れ:1兆0390億円などなど。
また、「成長力の強化・高度化に資する国内投資を促進する」として、先端半導体の国内生産拠点の確保:6322億円、半導体の安定供給の確保:4376億円、「宇宙戦略基金」の創設:3000億円などが含まれている。半導体事業への支援だけでも1兆円を超え、「成長力の強化・高度化」には3兆4375億円が支出される。物価高対策としての低所得世帯向け支援(1兆0592億円)をはるかに上回る。
半導体事業への支援は、補正ではなく本予算で扱われるべきものである。しかも、それが財政支出の最優先項目にされてよいのかは、根本的に疑問である。最優先されるべきは、医療・介護・子育てなど社会保障への支出の大幅な拡大である。産業への財政支援という点では、ケアの事業に加えて再エネと食料自給への支援こそ重視されねばならない。
見当違いでデタラメな財政支出拡大を正当化するのが、「まだデフレを脱却していない」というごまかし、「デフレの亡霊」なのである。
※注4:菅野幹夫「もうデフレと言うなかれ」(日経新聞23年12月6日、「中外時評」)
注5:白川「脱炭素化に逆行 ガソリン価格抑制のための補助金の継続」(PP研WEB23年10月4日)
税収が増えているはずなのに、新たに8.8兆円もの国債を増発するカラクリ
13.1兆円もの大型補正予算の財源の7割弱(67.2%)は、新たに8.8兆円の国債発行で賄われる。その結果、23年度の新規国債の発行額は44兆4980億円に増え、4年連続で40兆円を超える(22年度は62.5兆円、20年度は108.6兆円、16~19年度は平均35.8兆円)ことになる。国債依存度は、当初予算の31.1%から34.8%に高まる。昨年度の44.9%よりは低下するが、19年度の35.4%に並ぶ。23年度末の国債発行残高は、1075兆7千億円に達する。
政府は、過去2年間の所得税・住民税の税収が3.5兆円増えたので、定額減税で「還元」すると説明してきた。ところが、松本財務相が「税収増分はすでに使っている。減税するなら国債を発行しなければならない」(衆院財務金融委員会、11月8日)と、あっさりバラシてしまった。税収増分を減税の形で「還元」するという贈り物がとんでもない偽物であることが白日の下にさらけ出された。減税=「還元」するために、新たに借金しなければならない破目になったわけである。
国債発行残高が1000兆円を超えて積み上がることは、金利上昇が避けられない時代、「金利ある世界」に入っている現在、国債の利払い額が急増するという大きなリスクを抱える。アベノミクスの下で大量の赤字国債を発行し続けることができたのは、日銀の超金融緩和によるゼロ金利政策によって利払い費が7兆円台で横ばいしたからだ。だが、長期金利が上昇すれば利払い費が急増し、社会保障関係の支出を圧迫することになる。
日銀は10月31日の金融政策決定会合で、長期金利の上限を「1%をめど」とすると、1%超えことを容認した(1%以下に抑えるための国債の大量購入=「指し値オペ」をやめる)。3月末には0.3%台だった長期金利は、9月末には0.7%台に上昇し、直近では0.8%台で推移している。長期金利が1%を超えて上昇することは避けられないだろう。
「金利が上昇し始めたら政府の利払い費用は急増する。そうなったら大変なことになる。警戒しておいたほうがいい」。この真っ当な警告は、誰あろう黒田前日銀総裁のこの夏の発言である※6。開いた口が塞がらないのだが。
23年度の国債費は25.3兆円で、うち利払い費は8.5兆円であった。24年度の国債費は金利上昇を反映して28.1兆円、うち利払い費が9.6兆円と大きく増える。さらに内閣府の試算(23年7月)では、2032年度には長期金利が3.2%に上昇するため国債費は38.5兆円、うち利払い費は18.4兆円に膨れ上がる。
税収増分を減税の形で「還元」して人びとの歓心を買おうとした岸田の策略は、実は借金を積み上げ利払いの急増を招くものでしかない。
※注6:原 真人「『税収増を還元』というごまかし」(朝日新聞10月7日「多事奏論」)
経済成長神話に憑りつかれた岸田
岸田は、「デフレ脱却」の先に「成長型経済」が来るというバラ色の幻想をふりまいている。「『低成長・低賃金・低成長のコストカット型経済』から『持続的な賃上げや活発な投資が牽引する成長型経済』への変革」を3年間でやり遂げる、と(所信表明演説、10月23日)。
岸田の目論見は、「物価上昇を十分に超える持続的な賃上げ」の実現によって可処分所得を引き上げて消費支出を上向かせ、「物価と賃金の好循環」、「消費と投資の好循環」に移る、というものである。もう1つは、「供給力の強化」である。「負のGDPギャップが解消されつつある中、供給力を強化し、日本経済を一段高い成長軌道に乗せていく」(「総合経済対策」)。補正予算に盛り込んだ半導体事業への支援は、その方策である。
岸田が何よりも力説するのは、持続的な賃上げの実現である。23年の賃上げは、1人あたり3.2%で前年より1.3㌽増え、1999年以降では最も高かった。企業の経常利益は、円安の恩恵を受ける輸出向け大企業を中心に4~6月期、7~9月期のいずれも過去最高を更新している。したがって、企業が賃上げを許容する余力は十分にある。また、物流・交通や介護などの分野で表面化している労働力不足も、賃金を押し上げる作用をするだろう。
しかし、米国でUAWが長期ストによって25%の大幅な賃上げを獲得したのとは対照的に、日本では労働組合がこのチャンスを活かしてストライキによって賃上げを実現する力を欠いている。そのため、賃上げができるか否かは、もっぱら企業側の個別の条件や裁量に委ねられることになる。そこで、政府の果たす役割が問われるが、岸田政権は「持続的な賃上げ」を呼号するだけで、有効な方策を採ろうとしない。効果の乏しい賃上げ税制の拡充を持ち出すが、正規・非正規や男女間の賃金格差解消、最低賃金の抜本的な引き上げ、介護・医療・保育労働者の大幅な賃上げなどに大胆に踏み込もうとしない。その意味で、物価上昇を超える賃上げが実現できるかどうかは不確実・不透明である。
さらに、大きなカベは、賃上げが実現されたとしても消費支出が飛躍的に伸びるのだろうかという問題である。

「家計調査」で見ると、消費支出(実質増減率)は、コロナ危機からの回復によって2022年にはいったん上向いたが、23年に入ると再び低下している[図]。その直接の要因は、賃金上昇が物価高に追いつかず、物価高騰、とくに食料など生活必需品の高騰が人びとを節約志向に走らせていることである。
しかし、消費支出が低迷している根本的な理由は、将来の生活保障・社会保障への不安の広がりなのだ。介護をとってみても、保険料は上がっても提供されるサービスは切り縮められている。介護を担う人材が高齢化し(ホームヘルパーの4割弱が60歳以上)、圧倒的に人手が不足しているから、サービスを受けられなくなる恐れが大きくなっている。したがって、多くの人びとは消費を節約し、賃金が少し上がっても貯蓄に回す「自己責任」型生活防衛に走ることになる。
問題の根本的な解決のためには、経済成長神話と訣別して《ケア中心の経済・社会への転換》を強力に推進する必要がある。医療・介護・子育てのサービスが無償で受けられる、また公共交通機関が低料金で利用できる。広告に踊らされて新しいクルマや流行のアパレルを買い込む個人消費の活発化ではなく、共同で消費したりシェアリングするサービスやモノがどんどん広がる。CO2排出の削減を促進すると同時に、安心を保障する。そうした新しい質の消費のあり方への転換が求められている。「過剰消費」型の生活様式を変革して、「脱成長」へ移るということにほかならない。
いま、求められる経済政策は何か
最後に、いま求められる経済政策を簡単に提案しておきたい。
第1に、インフレが進行している現在、十分な生活支援金(物価手当)を低所得層および中所得層に対して給付する。公共交通機関の運賃を引き下げるための補助金を支給する。逆に、所得税減税は行わない。ガソリン価格抑制のための補助金支出はやめる。社会保険料は引き下げて、代わりに累進性のある税負担を増やす。
第2に、賃上げを促進する。具体的には、正規・非正規、男性・女性の賃金格差解消のために違反企業に罰金を課し社名を公開する。最低賃金を時給1500円に早急に引き上げる。公共部門の労働者の賃金を抜本的に引き上げる。
第3に、ケア中心の経済・社会に転換するための財政支出を大幅に増やす。まず介護・医療・保育・子育てに従事する労働者の賃金を抜本的に引き上げる。介護保険料を引き下げて、逆により多くの税を投入する。防衛費の増大を止め、縮小していく。
第4に、脱炭素化と農業の再生のために財政支出を拡大する。再エネの拡大への支援、国内産の農産物価格の引き上げ、学校・保育所・介護施設・病院など給食への有機農産物の供給促進の支援など。逆に、ガソリン税を引き下げずに組み換えて炭素税(地球温暖化対策税)を大幅に引き上げる。
第5に、富裕層と大企業に対する課税を抜本的に強化する。富裕層に対して金融所得課税を強化する(勤労所得課税なみの累進制の導入)、大企業に対しては法人税の累進課税化、内部留保への課税導入を行う。
(2023年12月8日)